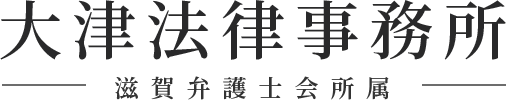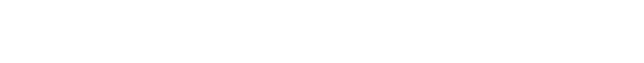揉めている相続放棄
揉めている遺産分割に関する『よくある相談』
揉めている遺産分割の『よくある相談』
- 被相続人と同居していた相続人が、どのような遺産があるか教えてくれない。
- 長男がほとんどすべての財産を取得すると言っている。
- 遺産分割協議書が送られてきて、実印を押せと言ってくる。
- 相続人が話し合いになると感情的になってしまい、話が進まない。
- 相続税の申告に必要だからと言われて、仮に協議書に判子を押して欲しいと言われている。
- 相続税の申告期限が近いが、遺産分割協議がまとまりそうにない。
揉めている遺産分割への弁護士の関与
相続では、被相続人が亡くなると、その相続人の方が、被相続人の方の財産・負債を引き継ぐことになります。
相続人の方が複数いると、だれが、どの遺産を取得するかを決める必要があり、その取得する財産をきめることを遺産分割といいます。
遺産分割は相続人全員の同意が必要です。相続人の一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しません。
そのため、揉めている遺産分割は、相続人間の利害関係を調整するのが
複雑になり、遺産分割を解決するまでの労力・時間の負担がより大変になる傾向があります。
揉めている遺産分割は、通常、①一人の相続人の代理人になる場合には、他の相続人と、②共通の利害がある複数の相続人の代理人になる場合には、代理人にならなかった他の相続人と話し合いをして、話し合いがまとまらなければ、調停、審判等を通じて、遺産分割の成立に向けて、対応します。
事案により相続税等税金の問題が生じる事案では、税理士と共同して対応します。
遺産分割が解決するまでの流れ
STEP1 相続人の調査、財産目録の作成
相続人の調査と遺産の調査を行う。
登記簿謄本・固定資産評価証明書・通帳等を収集して、財産目録を作成します。
STEP2 負債が多い場合は相続放棄を検討する
相続放棄するか否かは、基本的には積極財産と消極財産の額を比較して決定することが一般的です。
STEP3 ご依頼者の希望を踏まえた上で、遺産分割案を作成して、他の相続人に提案・交渉をします。
遺産の調査結果を踏まえ、ご依頼者のご希望を伺い、他の相続人に提案する遺産分割案を作成します。
代理人弁護士が、ご依頼者と協議して作成しました遺産分割案を他の相続人に提案して、遺産分割が成立することに向けて協議をしていきます。
他の相続人との協議は代理人弁護士が行いますので、ご依頼者の方が協議をする必要がありません。
STEP4 協議がまとまる見込みが乏しければ、遺産分割調停を申し立てます。
STEP5 相続人間の遺産分割の合意が成立した場合
協議の場合には、依頼者代理人が遺産分割協議書を作成して、他の相続人から署名・押印してもらいます。
調停まで至っていた場合には、遺産分割案を作成して、調停期日で遺産分割が成立します。
STEP6 遺産分割内容を実行する。
遺産分割協議が成立していた場合には、遺産分割協議内容に応じた実行を行います。
また、調停が成立した場合には、調停内容に応じた実行を行います。
例えば、不動産を名義移転登記したり、預貯金を分配したりします。
サービス内容(揉めている遺産分割の場合)
相続関係図の作成
相続人確定のための戸籍謄本・原戸籍等を収集して、相続関係図を作成する。
財産を調査して財産目録を作成する。
他の相続人との協議
弁護士が、ご依頼者の意向・法的な見解・実務的な経験に基づき遺産分割案を作成し、他の相続人と協議をしていきます。
協議が成立すれば遺産分割協議書を作成しますが、協議が成立しない場合には、遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停の申し立て
協議が成立しない場合に申し立ていたします。
遺産分割内容の実行
①相続税申告・登記手続について
お知り合いの司法書士・税理士がいなくても、弁護士が適任者の税理士・司法書士を確保致します。
その上で、弁護士が窓口になって、相続税申告・不動産登記を進めるのでご本人の事務処理の負担は軽減されます。
②相続で取得した預金について
遺産分割で取得した預金に関しては、弁護士が預貯金解約手続きを代理して行うため、ご本人が銀行の窓口に行って解約手続きを行う必要はありません。
Q&A‐よくある質問‐
Q1 遺産分割の話が進まず困っていますが、どうしたらよいですか。
A まずは、弁護士にご相談ください。
話が進まない原因、本件の問題点、現在の状況について、整理をしていきます。そして、今後の方針についてアドバイスいたします。
また、弁護士に相談することで、自分の置かれている状態を客観的に認識でき、今後の遺産分割の進め方を見直すきっかけになります。
まずはお気軽にご相談ください。
Q2 相談のときはどの様な資料を持っていけばいいでしょうか?
Aまずは、手元にある資料だけをお持ちください。
あと、以下のメモ書きをお願いしています。
①相続関係図
②ご相談者が把握している範囲の財産関係
Q3弁護士と話すのは初めてなので、緊張します。どうしたら良いでしょうか?
A特に、身構える必要はありません。緊張せずにお越しください。
Q4他の相続人から遺産分割協議書が送付されてきて、その相続人から実印を押して、印鑑証明書を付けて返送しろと、しつこく電話をしてきます。どうしらたよいでしょうか?
A送られてきた遺産分割協議書の内容を確認して、納得いかない場合には、絶対に署名・実印で押印しないでください。
そして、自分で話し合いができないと思うようでしたら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
Q5私には長男がいますが、その長男が実家を継ぐから遺産を全部相続するので、その内容の遺産分割協議書にハンコを押すよう言ってきます。どうしたらよいですか。
A長男のこのような主張は、現在の民法では認められません。あなたにも、法律で認められた法定相続分があります。
しかし、当事者同士の話し合いでは長男は考えを曲げない場合が多いので、このような場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
Q6不動産の分け方ですが、不動産を取得したいと考えている他の相続人から、不動産の評価額は固定資産税評価額にしようと言ってきました。この不動産の評価方法に問題はないでしょうか?
A一般的に、固定資産税評価額は時価より安いので、その不動産の評価方法の提案は断った方がよい場合が多いです。
特に、一人の相続人が、その不動産を取得して、他の相続人に代償金というお金を支払う内容の遺産分割の場合、代償金の金額は、不動産の評価額が低いと代償金も安くなります。固定資産税評価額は時価より安い場合が多いので、不動産の評価方法を固定資産税評価額で行うと代償金は安くなることが多いです。
したがって、その不動産の評価方法の提案は断った方がよいと思います。