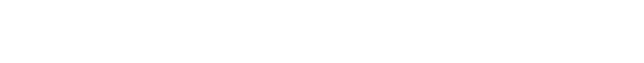遺言について
1 遺言の性質
⑴ 要式行為
方式に反すると効力が生じない(民法960条)。
⑵ 遺言は遺言者がいつでも遺言を撤回することができる
遺言者は理由なく遺言の方式に従っていつでも撤回できる(民法1022条)。
⑶ 遺言は、遺言者の死亡の時から効力が生じる(民法985条)
* 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法994条1項)。
* 「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させる者とされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力については、最高裁判所が以下のように判断している。
「上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である」(最判平成23年2月22日)。
⑷ 遺言で法的効果を生じるのは法定事項に限られる。
* 例えば、兄弟は仲良く母親を助けることと、離縁する意思を表示するなど法定遺言事項以外の遺言があっても、法律上効力が生じない。
* なお、「相続させる遺言」は直接の規定はないが、判例は、遺産分割方法の方法の指定(民法908条)と解釈している。
2 普通方式遺言
遺言は、「自筆証書、公正証書又は秘密証書によってこれをしなければならない。」(民法967条)と定め、その方式を3種類に限っている。この方式に従う遺言を普通遺言方式という。
3 遺言能力
満15歳に達した者は遺言をすることができる(民法961条)但し、遺言の内容を理解し、その結果を弁識し得るに足りる意思能力が必要である。
特に高齢者の遺言で問題となり、公正証書遺言でも、裁判所により効力が否定される場合がある。
*遺言能力に関する裁判例「遺言には、遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力(意思能力)すなわち遺言能力が必要である。
遺言能力の有無は、遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移、発病時と遺言時との時間的関係、遺言時と死亡時との時間的間隔、遺言時とその前後の言動及び精神状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者の関係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無等遺言者の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項(遺言の内容)を判断する能力があったか否かによって判定すべきである」 (東京地方裁判所平成16年7月7日判決・判例タイムズ1185号291頁)。
4 遺留分と遺留分減殺請求
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保障された相続財産の一定割合をいう。
遺留分減殺請求とは、遺留分権利者が遺留分を侵害された場合、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺留分侵害行為(遺贈・贈与)の減殺を請求する権利このとをいう(民法1031条)
5 相続させる遺言と遺贈
⑴ 相続させる遺言
ア 具体例
- ・全財産をAに相続させる。
- ・土地甲をAに相続させる。
イ 最高裁判所の立場
- ・特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させる遺産分割方法の指定(民908条)であり、
- ・遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せず、被相続人の死亡時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、
- ・当該遺産については遺産分割の協議又は審判を経る余地はない。
⑵ 遺贈
ア 遺贈とは、被相続人が遺言によって、無償で自己の財産を他人に与える処分行為(民法964条)。
イ 包括遺贈 包括遺贈とは、遺産の全部又は一定割合で示された部分の遺産を受遺者に与える処分行為。
具体例
- ・遺言者の財産全部を包括してAに遺贈する。
- ・遺言者の全財産の2分の1をAに包括して遺贈する。
ウ 特定遺贈特定遺贈とは、特定の具体的な財産的利益を対象とする遺贈である。
具体例
- ・土地甲をAに遺贈する。
エ 包括遺贈と特定遺贈の主な違い包括遺贈は、債務の承継を伴う。
包括受遺者は、相続人ではないが、相続人と同一の権利義務を取得するから(民法990条)。
* 相続させる遺言の場合の遺言の対象者は、遺言作成時において、第1順位の相続人のみでる。
それ以外の者に対して遺言で財産処分するには、遺贈で行う。